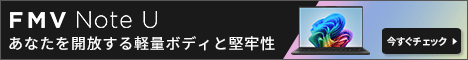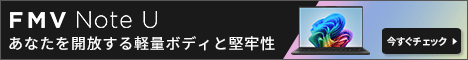|
大神神社、いくつかの疑問
最初に鳥居が見えた。鳥居の両脇には備前焼で造られた2対の狛犬が鎮座していた。
備前焼の狛犬は全国的には珍しいだろうが岡山市近郊では特別珍しいものでもなく、あちこちの神社で比較的よく見かけるから別段驚きも、とりわけ興味を持ったわけでもない。

それより鳥居を見て「おやっ」と感じたことがいくつかあった。
1点は鳥居が道路脇にあること。
本来なら鳥居の下に道路が通っているはずだが、この鳥居の幅や高さでは車が通れないかギリギリ通れるかというぐらい狭いため、本来の道(旧道)の横に道幅が広い新道を造ったと思われる。
2点目は神社が参道の延長線上に存在しなかったこと。
参道は参拝者が神社へお詣りする道だが、神様が通る道でもある。
故に神社が鳥居の延長線上に存在しないのはおかしい。
たまに参道が曲がっていたりする神社が存在するが、それは後世、土地改革その他の理由で神社が本来あった場所から移されたからだ。
大神神社は鳥居から神社までの間が新興住宅地になっているから、宅地開発で本来の場所から移動されたと思われる。

3点目は神社が平地にあったこと。
これにも強い違和感を覚えた。
神様を祀る場所は高い所にある。歴史ある神社は拝殿に至るまでに長い石段があったり、小高い丘の上や鎮守の森と言われるような場所にあるのが一般的だ。
一部、平地に存在する神社もあるが、それらのほとんどは明治維新前後以降に造られた新しい神社だ。
出雲大社は平地のように見えるが建物そのものは現在と違ってかなり長く高い傾斜の先にあった。
このようなことから本来、大神神社は参道の真っ直ぐ延長線上の山の中腹辺りにあったと思われる。それをいつの時代か定かではないが下に移し、しかも参道の延長線からズレた場所に移し替えたと考えられる。
(3)に続く
|